ジャンボタニシの被害防止対策
ジャンボタニシ(和名:スクミリンゴガイ)は、南米原産の暖かい所に生息する巻き貝です。
食用目的で輸入されたものの各地で野生化し、水稲を食害するほか、食欲旺盛で繁殖力が強いため、急速に被害が拡大します。また、水路や稲の株などに濃いピンク色の卵塊を産み付けるため、景観を損ねます。
薬剤散布や耕種的防除などにより、地区全体で防除に取り組むことが被害軽減につながります。
特徴
- 長いひげ(触角)を持ち、貝のらせん下部の層が他の層と比べ広いのが特徴です。
- 成貝は5センチメートル程度まで育ち、通常のタニシと比べると大型です。
- 濃いピンク色の卵を産みます。

ジャンボタニシの成虫

ジャンボタニシの卵塊
被害防止対策
通年対策:貝や卵塊の駆除
- 見つけ次第補殺します。
- 卵塊は、空気中でしか孵化できないため、水中に落とすと効果的に駆除できます。
(注意)寄生虫がいる恐れがあるため、貝は素手で触らないでください。
取水期間対策:侵入防止
- 取水口にネットや金網を設置して、侵入を防ぎます。
- 特に、代かき前の入水時や中干し後の入水時に侵入が多いため、この時期に設置すると効果的です。
苗の移植後:食害防止
- ジャンボタニシは水の深い所を好み、浅い所では稲を食べることができません。
水深を4センチメートル以下にして、田面を平らにすることで被害を防げます。 - 移植直後の柔らかい苗を好んで食べますが、苗が育つと食べなくなります。
早めの移植により苗を大きくすることで、食べられるのを防ぐことができます。
冬季対策:耕起粉砕・水路の泥上げ
- 田んぼを水上げして乾燥させ、耕運することで、土の中で越冬するジャンボタニシを駆除できます。
- 水路の泥の中でも越冬するため、泥上げをすることで駆除できます。
- 地区全体で実施すると効果的です。
関連ファイルダウンロード
チラシ(ジャンボタニシによる被害を防ぐために:農林水産省チラシ)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農林係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231








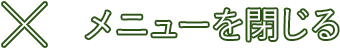
更新日:2022年03月14日