令和7年度施政方針
令和7年度施政方針(全文)
令和7年3月4日に開会された令和7年第1回(3月)町議会定例会の冒頭において、令和7年度の町政運営に対する町長の基本的な考え方である施政方針を表明しました。
施政方針全文
令和7年第1回定例会の開会にあたり、令和7年度において宇治田原町政に臨みます所信の一端を述べさせていただきます。
私は、先の町長選挙におきまして、住民の皆さまからのご支援により、歴史と伝統に培われた宇治田原町の第19代町長として町政を担わせていただくこととなりました。
多くの住民の皆さまからご支援をいただきましたことに、深く感謝申し上げますとともに、改めて期待の大きさと、責任の重さに身の引きしまる思いでございます。
開会にあたり、諸議案をご提案申し上げます前に、私の任期の始まりとなります令和7年度において、宇治田原町政運営の先頭に立たせていただきます、私の町政にかける思いをお伝えし、議員各位をはじめ、住民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
私は、先の選挙におきまして町政運営へ臨むにあたり、住民目線、未来志向、対話重視を基本姿勢とし、新たな発想で未来を描く4つの新ビジョンをお示しさせていただきました。
1つ目「町政の見える化」では、わかりやすい情報発信と対話機会を創出し、宇治田原への想いを伝播してまいります。
2つ目「稼げるまちを具現化」では、宇治田原町から全国に向けたまちの魅力発信を通じて、新たな働く場の創出等を仕掛けてまいります。
3つ目「公共交通の充実」では、学生・高齢者の移動ニーズに寄り添い、利便性を向上させ、この町での住みやすさを守ってまいります。
4つ目「若者・働き世代に選ばれるまちへ」では、仕事と健康を支えて夢の実現を応援する取組を通して、若者・働き世代に選ばれるまちを目指してまいります。
このビジョンを進めていくために、「未来創造計画」として、ふるさと納税を通じて稼げる自治体を目指してまいります。寄附額の増収を目指し、いただいた寄附を財源として子どもたちの夢を応援する。この未来への投資が、まちの魅力発信と、関係人口の増加につながり、そのつながりによって企業とのマッチング機会を創出し、企業版ふるさと納税や、新たな企業を呼び込んでいく、そのような好循環を生み出してまいりたいと考えております。
令和6年に発表された人口戦略会議のレポートで、宇治田原町は消滅可能性のある自治体に分類されました。この危機感・課題を議会、住民の方々と共有し、100年後も宇治田原町がここに残っていくために、小さな町だからこそ、大きな変化ができると信じ、未来を創造する新しい一歩を踏み出してまいりたいと考えております。
私の任期の最初となります令和7年度予算は、「未来へ 基礎づくり予算」と題し編成を行ったところであり、本議会にご提案しております第6次となる新たなまちづくり総合計画の初年度として、安心安全や少子高齢化対策をはじめ、都市基盤整備のほか、教育充実などの基本となります各種施策を計上したところであり、主要な施策の概要につきまして、「第6次まちづくり総合計画」の4つの「まちづくりの目標」と「行政の基本姿勢」に沿ってご説明申し上げます。
まず、災害時の暮らしの不安要因を減らすとともに、保健・医療・福祉の充実を図り、安心して暮らせる「やすらぎのまちづくり」であります。
地震などの自然災害へ備え、これからも安心して暮らせるまちを目指すため、防災対応力強化として、指定避難所の備蓄倉庫を増設し、簡易折りたたみベッドなどの災害用備蓄資材の更なる配備により、避難所物資の充実を図り、防災対策に取り組んでまいります。また、地震への備えとして木造住宅の耐震改修に係る補助や、子どもたちの交通安全意識の高揚と交通事故発生時の被害軽減を図るため、自転車運転時のヘルメット購入に対する支援も引き続き行ってまいります。
消防の充実では、令和9年度の運用開始に向け、消防体制の強化等が期待される京都府南部消防指令センターの共同運用に向けた取組を進めるとともに、本町の消防拠点である京田辺市消防署宇治田原分署の長寿命化への取組として、大規模改修に向けた設計等に着手してまいります。
また、災害用毛布等が備蓄できる機能も兼ね備えた湯屋谷コミュニティ消防センター建設に向けた取組を進め、地域における消防防災力の強化も図ってまいります。
誰もが安心して健やかに生活できる想いを実現していけるよう、全年齢層を対象とした住民参加型イベント「うじたわら健活フェスタ」の開催を通じて、健康づくりに関する様々な情報を発信・提供することで、住民が自主的かつ継続的に健康づくりに取り組む意識を醸成してまいりますとともに、健康増進と食育推進の指針となる「健やかうじたわら21プラン」の改定に取り組んでまいります。
また、がんに罹患された住民の方への支援として、がん治療に伴う心理的負担の軽減、社会参加促進などを目的とした補整具等への助成に新たに取り組むとともに、各種健(検)診については、受診率向上のため、住民のニーズや課題を捉えたアプローチにより、受診の習慣化と自らの健康づくりの動機づけを促してまいります。
高齢者の健康づくりと疾病予防を推進する観点からは、各地域の通いの場に保健師が赴き、フレイル予防に着目した講座や啓蒙、健康相談に取り組みます。また、健診結果等から低栄養のリスクがある方や、健康状態の不明な方には、面談等により現状の確認を行う中で、関係機関等と連携し、適切な支援・医療に繋げる切れ目のない取組で、住民の健康寿命の延伸を図ってまいります。
帯状疱疹ワクチン接種につきまして、新たに予防接種法に基づく定期接種に位置づけられますことから、希望される方が予防接種を受けられるよう、医師会等と連携し、適切に対応してまいります。
地域福祉においては、今後の地域福祉の方向性を位置づけ、地域共生社会の実現に向けた指針となる「第4期地域福祉計画」の策定に取り組んでまいりますとともに、地域福祉の実践者であります民生児童委員協議会、社会福祉協議会、またボランティアの方々の活動を支援し、地域の絆の源泉とも言うべき地域ぐるみの支え合いの基盤づくりを進めてまいります。
本町の高齢化率は既に32%を超え、超高齢社会を支える介護保険・高齢者福祉制度の役割はますます大きくなります。
要支援・要介護者の認定率は全国、また、京都府平均と比較し低位に推移しているところですが、高齢者が住み慣れた地域の中でつながりを持ちながら生き生きと暮らし続けていけるよう、介護予防事業等を通じて、引き続き生活の質の向上に取り組んでまいります。
また、障がいのある方々が住み慣れた地域の中で安心して生活できる、障がい者基本計画の理念に掲げる「共生のまち」実現を目指し、「地域自立支援協議会」を通じて課題を共有しながら、地域の実情に応じた支援体制の整備に努めてまいりますとともに、関係機関をはじめ、地域や住民と共に各種福祉施策・事業を展開し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、すべての人にとって暮らしやすい、宇治田原の実現を目指してまいります。
2つ目の柱、道路などの都市基盤整備をはじめ、交通環境の充実や、持続可能性の創出に向けた自然環境保全など、より良い未来を創造する「つながりのまちづくり」であります。
鉄軌道のない本町では、近隣市町とのつながり、町内交通の利便性向上のための都市基盤として、国道307号をはじめ宇治田原山手線など、まちづくりの誘導軸となる道路整備は重要であります。
宇治田原山手線が全線開通すれば、(仮称)宇治田原インターチェンジのほか、近隣2つのインターチェンジからもそれぞれ10分以内のトリプルアクセスが可能となるだけでなく、京都府南部の市町をはじめ滋賀県へのアクセスも向上するなど、交通の要衝としてまちのポテンシャルは大きく引き上げられます。災害時における道路代替機能の確保はもちろんのこと、時間距離の飛躍的な短縮による日常生活圏の拡大や、京都府南部地域の東西軸として、企業活動にとっても高い利便性を有する道路となります。新名神高速道路開通のインパクトを確実に地域内に引き込むためにも、「宇治田原山手線」の早期全線開通に向けた取組を継続してまいります。
また、インフラ整備の効果を最大化するには、道路が有機的に接続される必要があります。新名神高速道路開通の効果をまちづくりにつなげ、安全で災害に強い道路整備を計画的に進めるため、宇治田原山手線と関連する「宇治田原工業団地線」の整備を、引き続き進めてまいりますとともに、生活道路の安全性確保のため、町道の整備・改良をはじめ、道路施設の長寿命化対策にも計画的に取り組んでまいります。
住民の町内移動や民間路線バスへの接続性向上と、持続性のある地域公共交通とするため、「💛(はーと)バス」、「💛(はーと)タクシー」の運行を引き続き行います。また、デコレーションバスや、フォトコンテストなど、多くの方に愛着を持ってもらえる「まちのバス」として利用促進を図るなど、「地域公共交通計画」に基づく各種交通施策を推進する中で、住民の皆さまのご意見を伺いながら、利用者の負担軽減策も含めて協議会における検証を継続してまいります。
日々の暮らしに不可欠なライフラインである水道水を安全かつ安定的に供給するため、地震に強い水道を目指して、耐震性のある水道管への更新を進めてまいりますとともに、足元の物価高騰対策として水道使用者の負担軽減を図るため、水道基本料金の減免により家計を支援してまいります。
また、公共水域の水質保全のため工業団地内における下水道管渠の整備及び汚水中継ポンプ場の耐水化に取り組みますとともに、公共下水道事業の経営基盤の強化を図るため、木津川流域下水道への編入につきまして、京都府及び関係市町と連携し、早期の事業着手に向け取組を進めてまいります。
3つ目の柱、地域の魅力を発信し、移住定住や農林商工をはじめとした産業振興、雇用の創出に取り組む「にぎわいのまちづくり」であります。
人口減少対策と定住化促進のため、京都ブランドと「日本緑茶発祥の地」という特性を活かしつつ、手厚い子育て支援や移住定住施策など、本町の強みを前面に打ち出し、星がきれいに見える自然豊かなハートのまちをPRする星空観測を新たなシティプロモーションとして展開し、ハートフルなまち『京都に、宇治田原町。』の魅力発信に引き続き取り組んでまいります。その受け皿として、「空家等対策計画」に基づく「うじたわらいく」お試し住宅や空家バンクのほか、若い世代の不安を少しでも解消するため、新婚世帯や首都圏からの移住就業者への支援など、移住定住に必要な生活・経済面のバックアップを行います。
また、SNSでの情報発信を強化し、移住を求めるターゲットを中心に、本町に興味・関心を持つ地域ファンの獲得に向け、戦略的なPRを進めてまいります。
この4月には「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪・関西万博が開催され、国内外から多くの方々が訪れることが期待されます。大阪・関西万博を契機とした、お茶を通じた交流の催しとして、西ノ山展望広場での呈茶イベントの開催や万博会場に設置される京都ブースにも出展し、本町の魅力発信と併せて観光誘客に取り組んでまいります。
宇治茶ブランドを支える生産地として、生産基盤の強化と高付加価値化に向け、優良品種への改植や機械設備の導入に対しても支援を行うとともに、高級茶生産地としての名声を高めるため、全国や関西の品評会への出品に取り組む出品茶対策協議会へも引き続き支援し、地場産業の振興を図ってまいります。
森林に囲まれた本町にとって、豊かな自然環境を後世に残していくためには、森林の適正な管理に取り組んでいくことが求められます。森林経営管理事業では、森林環境譲与税を活用しながら、現地調査や測量等を進め、森林整備施業を行うとともに 、林道の安全性、走行性や防災機能の向上を図るため、2号鷲峰山線の林道改良も行ってまいります。
野生鳥獣による農林作物の被害軽減・防除対策として、防護柵設置等に対し補助するとともに、3頭に増えた野猿対策に期待されるモンキードッグを引き続き活用する中で、耕作意欲の維持に努めてまいります。
ふるさと納税の取組では、町の特産品や地域ブランドを全国に発信し、関係人口の拡大とまちのブランド力向上、ひいては地域経済の活性化につなげることを目指し、力を注いでまいりました。順調に寄附額を増やし、2億円を超えるご寄附をいただくまでになり、子どもたちの未来を支援する貴重な財源となっております。ふるさと納税が地方創生に果たす役割も大きくなってきており、返礼品拡充やポータルサイトのブラッシュアップなどを通じて、地域ブランドの向上に努め、この取組を更に進めてまいりますとともに、企業版ふるさと納税につきましても、企業との連携の幅を広げ、新たな財源確保に繋げてまいりたいと考えております。
4つ目の柱、子どもたちがいきいきと成長できる環境や、教育の充実とともに、ふるさとへの想いの醸成などに取り組む「ハートのまちづくり」であります。
全国から寄せられたふるさと納税の寄附金は、「未来を担う子どもたち」の夢を応援することに優先的に活用させていただくことをお約束しております。「未来挑戦隊チャレンジャー育成プロジェクト」は、この仕組みに沿って取り組むもので、子どもたちの心にシビックプライドを醸成しながら、様々な分野への挑戦を後押ししてまいります。そして、取組のプロセスを可視化し、寄附者へのリターンとしてお示しすることで、つながりを生む好循環を築いてまいりたいと考えております。
町立保育所では、サーキット運動遊具の活用により、幼児期に体幹を鍛えることに着目した体づくりを行うとともに、保育者のスキルアップ研修などに取り組む中で、豊かな子どもの心を育む保育環境を充実させてまいります。
地域子育て支援センターでは、知育玩具等を活用した創作遊びを通じて表現力や想像力を養う講座や、楽しい外遊びで脳とからだの多面的な発育を促す講座の開催に取り組んでまいります。
小・中学校では、多様な国の文化や価値観に触れ、国際理解やこれからの未来について考えるきっかけとなるよう、子ども達が大阪・関西万博を体験できる機会を提供してまいります。
また、タブレット端末を活用したAIドリルの提供を継続いたしますとともに、プログラミング的思考力を高める授業や実社会での課題解決力を養うSTEAM教育にも取り組んでまいります。
寺子屋「うじたわら学び塾」では、地域ぐるみ・町ぐるみによる学びの向上を推進するため、教職員退職者や大学生、高校生などの参加のもと、学びの場を創出してまいります。
また、子どもたちが将来の夢に変身した姿を撮影するオリジナルヒーローポスター撮影会をはじめ、各世代にこの町ならではの取組を展開する、「未来挑戦隊チャレンジャー育成プロジェクト」のPRに努めながら、関係人口の創出につなげてまいります。
将来の変化を予測することが困難な時代にあっても、たくましく、しなやかに生き抜く力を身につけ、新たな価値を見つけ生み出す感性と探求力、他者との協働、表現を深める対話力を養いながら、一人ひとりが個性や能力を発揮できるフィールドを見つけ出すきっかけとなるよう、プロジェクトを進めてまいります。
安心して子育てできる取組として、これまでの健診に加えて、新たに年4回の5歳児健康診査を実施し、子どもの身体的・社会的発達状況を評価してまいりますとともに、子ども家庭センターを新たに設置し、妊娠期から子育て期まで幅広く相談・支援を行う体制を整え、子どもの健やかな成長への取組を進めてまいります。
仕事と子育ての両立を支える拠点、町立保育所「あゆみのその」は、人とのかかわりの中で、愛情・信頼感を得て、自主性を培うことを保育理念の一つとしています。保育士が愛情豊かに応答的にかかわることで愛着形成を図り、人に対する信頼感と思いやり、そしてそこから生まれる自己肯定感を育みながら、自信を持って意欲的に挑戦する心の保育に取り組んでまいります。
また、放課後健全育成事業では、田原児童育成施設及び令和6年度に新たに増設しました宇治田原学童施設において、遊びと生活を支援し、児童の健全な育成を図ってまいります。
小中学校教育環境の充実といたしましては、GIGAスクール構想で導入された児童、生徒のタブレット端末及び小中学校のICT機器の更新など、情報教育環境を整えてまいります。
高校に通学する生徒保護者が負担するバス通学費について、課税世帯助成割合を従来の2分の1からを3分の2に拡充し、更なる負担の軽減を図ってまいりますとともに、小中学生の保護者への物価高騰対策として、小中学校給食費の支援も行ってまいります。
生涯学習への取組としましては、「いつでも・どこでも・だれもが」生涯を通じて学びの楽しさを見つけられるよう、多様な情報提供に努めますとともに、グリーンライフカレッジでは、青少年から高齢者までニーズに沿ったメニューを取り揃えて、学びの機会を提供してまいります。
また、建設からまもなく29年が経過します総合文化センターにつきましては、舞台機構設備改修をはじめとした、さざんかホールの設備改修を行い、安全・快適に利用できる空間を提供してまいります。
現在、本町では約500人の外国人の方々が暮らしており、異なる文化・習慣への理解を深めるためには、言葉でのコミュニケーションも大切です。ボランティア養成講座を受講いただいた方々に運営いただく、外国人等を対象とした日本語教室を支援してまいりますほか、図書館事業として、ボードゲームなどを活用した外国人住民との交流を通じて相互理解を深める環境を提供するなど、多文化共生社会への取組を進めてまいります。
「行政の基本姿勢」では、住民が主役のまちづくりの取組の一環として、まちづくりへの対話機会の創出に取り組みますとともに、行政サービスや諸課題に関する様々な主体との連携強化の視点から、官民連携に向けた取組も進めてまいります。
新たな時代の舵取り役として、住民の皆さまからいただいた信託にこたえるべく、人口減少、厳しい財政状況など、宇治田原町が抱える諸課題に向き合い、この町のことを自分事として、これからの町をどうしていこうか、住民、事業者、行政が一緒になって考え、アイデアを出し合い、この町の未来を一緒に創っていきたいと考えております。
もっと住みやすくなる、もっと訪れたくなる、ずっとこの町を好きでいられる、新たな総合計画の将来像「もっと ずっと 宇治田原」に込めた想いと、私がお示しした「4つの新ビジョン」と「未来創造計画」が実現できるよう、皆さまの先頭に立って挑戦してまいりたいと考えておりますので、これからの本町の行政運営になお一層のご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。
令和7年3月4日
宇治田原町長 勝谷 聡一
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6631 ファックス:0774-88-3231








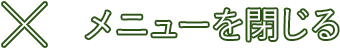
更新日:2025年03月04日