後期高齢者医療制度
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、75歳以上の方はすべてこの制度に加入して医療の給付を受けることとなります。
対象となる方
1. 75歳以上の方
2. 一定以上の障がいがあり、後期高齢者広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方(加入手続きが必要です)
※ 対象となられた方はそれまで加入していた医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
加入手続き
1. 75歳以上の方については、75歳に到達した日に自動的に加入となります。
加入手続きは不要です。
2. 一定の障がいがある方については、障害認定申請が必要です。障がいの程度がわかる書類(※)をお持ちのうえ、加入手続きをお願いします。
(※)障がいの程度がわかる書類
障害年金証書
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害保健福祉手帳 など
後期高齢者医療の被保険者資格を証明する書類
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証等について詳しくは
お医者さんのかかり方
京都府後期高齢者医療広域連合から「1人に1枚」、マイナ保険証をお持ちの方もそうでない方も、資格確認書(令和7年7月まで)が交付されます。
新たに75歳になる方には、75歳の誕生日までに資格確認書を発送します。
マイナ保険証または資格確認書(以下、「マイナ保険証等」と記載)は、医療を受ける時に必ず提示してください。
※医療機関にお持ちいただくもの
・74歳まで 「高齢受給者証」+「マイナ保険証等」
・75歳から 「マイナ保険証等」
医療機関での自己負担
医療費の自己負担割合
医療機関等で診療等を受けたときに窓口で支払う自己負担額(一部負担金)の割合は、世帯の所得や収入により1割、2割、3割に区分され、マイナ保険証等に登録または記載されています。
また、月の1日から末日までの1か月の自己負担額には限度額があります。
これらの自己負担の割合や限度額は、毎年7月に前年の所得等に基づき見直します。
※詳しくは、「医療費の一部負担について(後期高齢者医療制度)」をご覧ください。
自己負担額を軽減する制度(申請が必要です)
自己負担割合が1割となる方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口で提示することで、保健診療でかかる医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が軽減されます。
また、自己負担割合が3割となる方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口で提示することで、保健診療でかかる医療費の自己負担限度額が軽減されます。
※詳しくは、「医療費の一部負担について(後期高齢者制度)」をご覧ください。
医療費の支払いが高額になったとき
月の1日から末日までの1か月の自己負担額が限度額を越えた場合は申請書が送付されますので、2年以内に申請することにより、限度額を越えた額が支給されます。
なお、申請が必要となる初回のみで、2回目以降は初回に申請された口座へ振り込まれます。(再度申請が必要となった方へは申請書が送付されます。)
また、同一世帯内の1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険(後期高齢者医療、国民健康保険等)の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が規定の自己負担限度額を超える場合(越えた額が500円以下のときを除く)、翌年に申請書が送付されますので、2年以内に申請することにより、限度額を越えた額が支給されます。
保険料について
後期高齢者医療制度では、すべての方に保険料を負担していただきます。保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりに賦課されます。
制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)の被扶養者で、個人では保険料の支払いがなかった方も保険料がかかります。
※詳しくは「後期高齢者医療制度 保険料」・「後期高齢者医療制度 令和4・5年度保険料率について」をご覧ください。
健康診査について
後期高齢者医療制度の加入者を対象に、生活習慣病や心身機能の衰えの早期発見、健康の保持・増進を目的として、健康診査を実施しています。
検査費用は無料です。対象者へは6月下旬に個別に案内を送付します。
自覚症状のないうちに病気を発見し、早期治療をすることが大切です。元気ですこやかな暮らしを送るため、ぜひ健康診査を受診してください。
運営主体
後期高齢者医療制度では、全国の都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が制度の運営を行います。
京都府では、府内の全市町村が加入する『京都府後期高齢者医療広域連合』が運営主体となり、市町村は窓口業務などを行います。
【広域連合と市町村の主な役割 】
広域連合…運営主体
・マイナ保険証等の発行
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
市町村…窓口業務が中心
・マイナ保険証等の引渡し
・保険料の徴収
・申請や届出の受付
関連ウェブサイト
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231








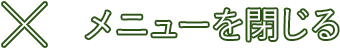
更新日:2023年07月10日